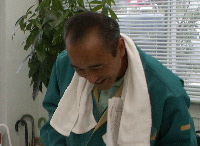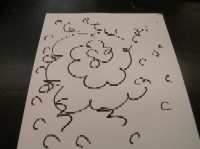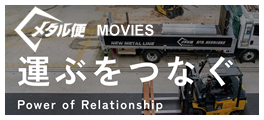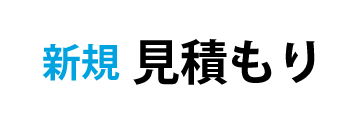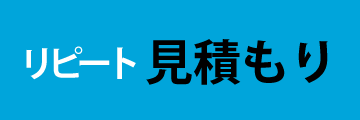関東
[ 関東 ] 動向
U氏より、最近の鉄鋼全般の動向を約1時間半ご教授いただく。海外ミルの寡占化が進む中のミッタルやポスコの動向とアジアの中におけるる日本のポジショニング、鉄鉱石やエネルギー事情、国内のメーカー・商社・流通の再編、トヨタ・現代自動車の戦略、国内景気、少子化の影響、市中品とひも付きのここ数年の傾向、鉄鋼難民の救済等・・・。大変に参考になった。日々の対策も大切だが、長期的動向を直視し、その中で我々が何が出来るかを再認識し、迷わず実行していくことが重要なんだなと実感した。
[ 関東 ] タイミング
今年10月より浦安がジャンプアップした実感をもっている。今年の2月~3月メタル便スタッフとして採用した4名が半年経過して、全員がかなりの戦力になってくれている。運行する車両総台数は微増だが、内容が違ってきている。常用車両の約50%が自車両となり、お客様に対して、よりメタル便ドライバーの顔が明確に認識していてだけるようになった。外部スタッフと内部スタッフのコンビネーションが出てきて、積込み現場も効率があがり、事務所スタッフにもゆとりがでてきた。振り返ると、結果として比較的物流の動きの少ない時期にスタッフ養成ができ、7月~の新規のお客様へのフォローにまわれた。タイミングが良かったかもしれない。今年もあと2ヶ月、年内はこの体制でいき、来年2月~3月に又増員していく。それに合わせ、新車も注文する。
[ 関東 ] 新規事業
メタル東海の渡辺さん、メタル関西の吉田さんはタイの物流事情の視察のため出張中、携帯電話が鳴らず静かな日々。夕方、コスモエイの市川社長から、失敗しない新規事業の取組み方を伝授いただく。①社長直結で行う ②若手が担当し、間に中間管理は置かない ③失敗は当たり前、失敗を恐れない。 新規事業は「企業の活力」であり、「新陳代謝」だと言っていた。先日知人と会話の中、新陳代謝のないある会社が話題になった。社員も高齢になり人数も減る、顧客数も年々減少していく企業。その話を聞いてO氏は即座に「理想的な会社だ」言われた。生きようとするのか、自然に死に向かっていくのか、中途半端が一番良くないかもしれない。
[ 関東 ] ユビキタス
メタル便グループを構成する各社のコミュニケーション能力が最近向上し加速されたきた気がする。対面・電話・eメールとうまく使い分け、所属・役職・地域の枠を乗越え、日常業務やプロジェクトの進行に向け、知恵の共有やお互いの長所を生かし役割分担がうまくいっている。方々で情報交換がされ、新ものが生まれていく。ユビキタスの語源はラテン語で、いたるところに存在する(遍在)という意味で、主にコンピュータの世界で使われるが、もし広範囲に使用することが許されるなら、我々のコミュニケーションは正にユビキタス状態かもしれない。私は吉田さんや渡辺さんと頻繁に連絡を取り合っているが、電話で二日間と日にちを空けると、1週間位会話していない感じがするし、二週間ぶりに会うと一年ぶりに会ったように思え会話が途切れない。それはそれだけ具体的な用件があり、スピードもアップしているからだ。
[ 関東 ] 集荷業務
午後1時から事務所内の4mのカウンターに、鉄鋼団地の当日集荷分の用紙が場所狭しと置かれる。帰ってきたドライバーが、集荷エリア・商品形状・出荷の最終受付時間を考慮して、各自の判断で優先順位を決めて集荷にまわる。今までは集荷先の会社名をメモに書き写し置いていたが、最近お客様から注文いただいた際のファックス用紙のコピーを必要な部分だけ切り抜いて置くようになった。その方が商品明細も分るし、お客様から注文いただいた用紙なので引き取りに行った際に間違いがない。ちょっとした工夫だが、毎日の仕事でこんなことの積み重ねが絶対差になっていく。
[ 関東 ] 調査会社
信用調査会社(二大大手の一社)が何処からか依頼を受け、来週調査にくる。通常考えると決してめずらしくもなく、どちらか言うと煩わしい仕事だが、社会的に認知された気がして何だか嬉しい。依頼主は同業者か?お客様か?仕入先か?・・・そんな事はどうでも良い。メタル便に対し、どこかの会社が数万円掛けて調査に値する会社だと認知されたのが妙に嬉しい。会社を立上げたころ飛び込みセールスの人でも、来社に対しても有り難く感じた時期を思い出す。
こんな物も運んでます。この商品は水濡れ厳禁。
[ 関東 ] ついでに積んで
メタル便を始めた当初、鉄鋼関連の新聞記者の方らか「お客様の扱い量が日々変動する。その変動部分をメタル便が受注すると言うことは、単にお客様の不効率な部分がメタル便に移動するだけで本質的な問題解決にはならないでは?」鋭い指摘であった。その問題とは正に5年間、毎日戦ってきた。でも何とか乗り越えてこれたのは、多くの物流会社の協力であった。鋼材の繁忙期は似通ってくるが、鋼材以外を取扱っている物流会社は結構余力があったりする。従来は繁忙期は応援として一日常用でトラックを数台入れる方法をとってきたが、最近は浦安近辺に着たついでに少量でも積んでもらえる物流会社との縁が広がったきた。その様な物流会社は主要荷主をもっており、一日の運賃収入はそこから確保できるのでし、少量の少額の運賃であっても気持ち良く引き受けてくれる。ここ半年の活動の中、古賀君が丁寧にその縁を広げつつある。今日も神奈川の運送会社にメタル便との接点を確認してきた。よきパートナーが一社一社増えていくのが有りがたい。
[ 関東 ] 砂山
海水浴で砂山を作る時、ある程度の高さになると崩れる。もっと高くする時は、土台の面積をひと回り大きくして作り直す。平成13年からのお客様別の売上を吉川氏に集計してもらい、気がついたことがある。上位1位~17位で全体売上の50%、以下18位~260位で残り50%を占める。18番目の会社は、全体の中の構成比は0.978%で1%にも満たない。5年経過した今、顕著にお取引が親密になっているお客様が一社一社と増えてきている。砂山に例えると基礎の土台作りが終わり、高さがでてきている状況。少しづつ高くなっても、メタル便の土台面積が非常に広いので簡単には崩れない。有り難い事だ。 カジ
[ 関東 ] 予兆
吉田さんと昼食中に話したこと。メタル便を運営していて最近感じることは、我々の持つ機能に大きな変化が表れているような気がする。今は何だか明確にはわからない。お客様がメタル便に要求される日々のお取引の中、我々が客観的に見たとき何をしているかにそのサインがあるような気がする。ハリウッド映画に例えると、天変地異が起きる前に主人公の身の回りに小さいが普段なかった出来事が立て続けに起きる、そんな様な予兆を感じる。 メタル便は今まで共同配送という切り口で、鋼材の小口配送プラットホームを作ってきた。それはこれからも変わらないが、どうも別の大きな副産物・無形の財産が出来つつあるような気がする。 お互いにしっかり分析していこうと言って吉田さんと別れた。 kaji
[ 関東 ] 群れる
1992年頃、慶応大学の藤沢キャンパスを十数社で見学した。当時インターネットは一部の研究者の間でのみ使われた時代で未知の存在だった。石井威持教授の説明の中、初めて聞くネット・サーフィンやモザイクなどの言葉や概念に感動を覚えた。説明の中「藤沢キャンパスの学生のレベルアップや革新の場は、授業やゼミの教室ではなく、学生が自由に集まる図書館・食堂・休憩時間の教室にある」と言われていた。ネット・AV環境が整った図書館(メディアセンター)で学生がワイワイガヤガヤする中、石井教授は我々に聞き取れるようにと大きな声で「重要なことは群れる場を作ること」と言われてた。メタル便にとって、そんな群れる場の一つが居酒屋かもしれない。今日、画像処理やシステムに詳しい定家君が社内にいたので、仕事のあいまに「こんな事したいけど、いいソフトある」とか、解らなくなって「これどうすれば良いの?」とか自由に聞ける時間があった。お陰様で半日で私のスキルもかなりアップした、これも群れることの一つかもしてない。